
当クリニックにおける糖尿病治療
糖尿病(ダイアベティス)とはインスリンが十分に働かないために、血糖値(血液中のブドウ糖の濃度)が上がる病気です。
血糖値が高くてもすぐに問題となることはあまりありませんが、長く放置することによって全身の血管が傷つき、のちに心臓病や、失明、腎不全、足の切断といった、より重い病気を引き起こす原因になることがあります。
これをメタボリックメモリーと呼び、早期の適切な介入により合併症の予防や進展を抑止することがとても大切です。
ところが、多くの糖尿病患者様は、病院受診では待ち時間が長い、自宅近くの開業医では夜受診できない、などの理由で適切な治療が受けられていないのが現状であります。
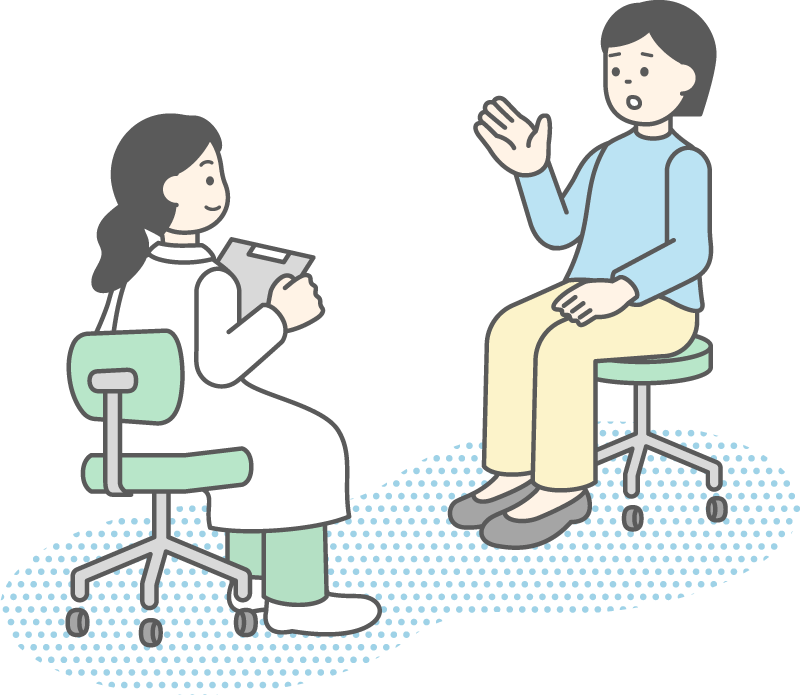
糖尿病(ダイアベティス)とはインスリンが十分に働かないために、血糖値(血液中のブドウ糖の濃度)が上がる病気です。
血糖値が高くてもすぐに問題となることはあまりありませんが、長く放置することによって全身の血管が傷つき、のちに心臓病や、失明、腎不全、足の切断といった、より重い病気を引き起こす原因になることがあります。
これをメタボリックメモリーと呼び、早期の適切な介入により合併症の予防や進展を抑止することがとても大切です。
ところが、多くの糖尿病患者様は、病院受診では待ち時間が長い、自宅近くの開業医では夜受診できない、などの理由で適切な治療が受けられていないのが現状であります。
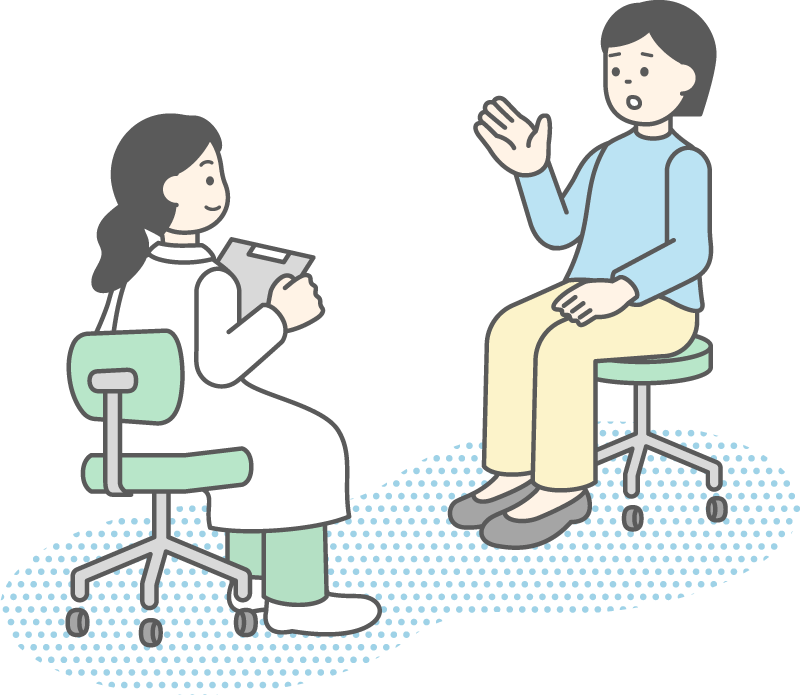

当院は、新宿駅南口0分とアクセスが良く、遅い時間まで診療を行い、空腹時血糖値、HbA1c値、尿検査などの院内迅速検査導入や院内処方(受診後院内でお薬を渡します)により利便性を追及しております。
また経験豊富な日本糖尿病学会認定糖尿病専門医と専門の資格を持つ療養指導士による、医学的根拠に基づいた無理のない正しい療養指導を提供いたします。
当院は、新宿駅南口0分とアクセスが良く、遅い時間まで診療を行い、空腹時血糖値、HbA1c値、尿検査などの院内迅速検査導入や院内処方(受診後院内でお薬を渡します)により利便性を追及しております。
また経験豊富な日本糖尿病学会認定糖尿病専門医と専門の資格を持つ療養指導士による、医学的根拠に基づいた無理のない正しい療養指導を提供いたします。

糖尿病合併症について
糖尿病は、高血糖状態が続くことによって、体のさまざまな部分に合併症を引き起こすことがあります。糖尿病の合併症は急性のものと慢性のものに大きく分けられます。これらの合併症は、早期に発見し適切な治療を行うことで予防または進行を防ぐことが可能です。
急性合併症
急性合併症は、急激に血糖値が異常に高くなったり低くなったりすることによって引き起こされる状態です。これらは命に関わることがあるため、早期の対応が必要です。
- 高血糖による昏睡(意識障害)
-
- 糖尿病ケトアシドーシス
- 高血糖が続くことで、体がエネルギー源として脂肪を分解し、その結果ケトン体が血液中に蓄積します。ケトン体は酸性であるため、血液が酸性に傾き、意識障害を引き起こします。症状としては、口臭がアセトン臭くなる、吐き気や嘔吐、頻尿、極度の渇きなどが現れます。特に1型糖尿病で発症しやすいです。
- 高浸透圧高血糖症候群
- 血糖値が非常に高くなり、体内の水分が血液中に引き寄せられて脱水が進行します。脱水症状が強くなると、意識混濁や昏睡に至ることがあります。
- 糖尿病ケトアシドーシス
- 低血糖性昏睡
-
血糖値が異常に低くなると、脳が必要とするエネルギー源(グルコース)が不足し、意識が失われます。低血糖の症状は、手足の震え、冷や汗、動悸、頭痛、めまいなどから始まり、最終的に意識を失うことがあります。これを放置すると昏睡状態に陥ります。
- その他
-
- 乳酸アシドーシス
- 乳酸が過剰に血液中に蓄積し、体内が酸性に傾く状態です。これは糖尿病治療薬のメトホルミンによる副作用や、アルコール多飲や腎機能が低下している場合に起こりやすくなります。重篤な場合、呼吸困難や意識障害が見られます。
- 感染症や脱水症
- 高血糖の状態では免疫力が低下し、感染症にかかりやすくなります。風邪や尿路感染症が悪化する可能性があり、放置すると重篤な症状を引き起こすことがあります。また、脱水症状が進行すると、血糖値がさらに高くなり、悪循環に陥ることがあります。
- 乳酸アシドーシス
急性の合併症は迅速に治療しないと命に関わることがあるため、自己判断せず、体調に変化を感じたらすぐに医師に相談してください。
慢性合併症
糖尿病が長期間続くと、全身に慢性的な合併症が起こるリスクが高まります。これらは時間をかけて進行し、早期に発見し管理することが重要です。
- 細い血管の合併症(細小血管症)
-
糖尿病に特有の合併症で、細い血管が損傷を受けることによって発症します。
- 糖尿病神経障害
- 高血糖が神経にダメージを与え、末梢神経が障害される状態です。主に足や手のしびれやチクチクした痛み、足の感覚が鈍くなることがあります。そのほか胃腸障害(下痢や便秘)、顔面神経麻痺、立ちくらみ、発汗異常など、いろいろな症状が現れてきます。
- 糖尿病網膜症
- 高血糖が原因で目の網膜にある小さな血管が傷つき、血流が悪くなります。これにより、視力低下や失明のリスクが高まります。網膜症は初期段階では自覚症状がないことが多く、目に特別な異常を感じなくても眼科を受診し、血糖コントロールの状態に合わせて定期的に眼底検査などを受ける必要があります。
- 糖尿病腎症
- 腎臓は血液を濾過して体内の老廃物を尿として排出する臓器で、水分(体液量)の調整を行い、タンパクなどの体に必要なものは排出されない仕組みになっています。腎症が進行すると、微量アルブミンやタンパクが尿に漏れ出てくるようになります。だんだん尿が作れなくなってくると、やがては人工透析と言って、機械で血液の老廃物を濾過し、人工的に尿をつくらなければならなくなります。現在、人工透析になる原因の第1位が、この糖尿病性腎症になっています。この合併症も自覚症状が無いままに進行しますので、早期に発見するために、定期的に尿検査をする必要があります。
- 糖尿病神経障害
- 大血管症(太い血管の合併症)
-
高血糖により動脈硬化が進行し、大血管にも影響を与えます。これにより、心臓や脳、足の血管に悪影響が及びます。血糖値以外にも血圧、血中脂質も適正に保つことが大切です。また、禁煙や肥満と運動不足の解消も動脈硬化の進行予防にはとても大切です。
- 心筋梗塞や狭心症(胸痛など)
- 動脈硬化が進行し、心臓への血流が悪くなります。これにより、心筋梗塞や狭心症(胸痛)が引き起こされる可能性が高まります。血糖コントロールの改善と共に、血圧や脂質の管理も重要です。
- 脳梗塞
- 脳の血管が狭くなることによって、脳梗塞のリスクが増加します。脳梗塞が発生すると、手足の麻痺や言語障害などが現れることがあります。
- 末梢動脈疾患(足病変)
- 足の血流が悪くなり、足の皮膚に傷ができても治りにくくなります。最悪の場合、足の壊疽や切断が必要になることもあります。糖尿病患者は定期的に足のチェックを行い、異常を早期に発見することが重要です。
- 心筋梗塞や狭心症(胸痛など)
- その他の合併症
-
- 感染症
- 糖尿病では免疫機能が低下し、感染症にかかりやすくなります。感染が重症化しやすく、風邪が肺炎に進行することもあります。血糖コントロールが悪いと、感染症にかかるリスクが高まり、回復も遅くなることがあるため、感染症予防に力を入れることが重要です。
- 歯周病や歯肉炎
- 高血糖状態が続くと、歯周病や歯肉炎の進行が早くなります。糖尿病では、口腔内の細菌感染が悪化しやすく、歯茎が腫れたり、出血したりすることがあります。定期的な歯科検診や歯磨きの徹底が推奨されます。
- 骨折や筋力低下(サルコペニア)
- 糖尿病は骨密度を低下させ、骨折のリスクを高めます。また、筋力の低下(サルコペニア)が進行しやすく、日常生活における身体機能の低下を引き起こすことがあります。適度な運動と栄養の摂取が予防には効果的です。
- 認知症
- 長期間にわたって血糖値が高い状態が続くと、認知症のリスクが高まることがわかっています。糖尿病患者は脳血管疾患やアルツハイマー病の発症リスクが増加し、認知機能の低下が進行する可能性があります。
- 悪性腫瘍
- 糖尿病は悪性腫瘍のリスクを増加させることが示唆されています。特に、膵臓癌や肝臓癌、大腸癌などが糖尿病患者で高頻度に見られることがあります。高血糖が慢性的に続くと、細胞の成長や変異が促進され、がんの発生リスクが高まることがあります。定期的な健康診断や早期発見が重要です。
- 感染症
合併症の予防と治療
糖尿病の合併症は、血糖値のコントロールを徹底することで最小限に抑えることができます。また、早期に発見し、専門医と連携して治療を行うことが大切です。定期的な検診を受け、健康状態を把握し、適切な治療を継続することが最も重要です。
- 血糖値のコントロール
- 食事療法、運動療法、薬物療法を組み合わせて血糖値を適正に維持することが大切です。
- 定期的な検診
- 眼科や歯科、フットケア外来など、定期的に専門医を受診し、がん検診を受けることが予防、早期発見に繋がります。
- 生活習慣の改善
- 健康的な食生活、禁煙、適度な運動、ストレス管理を行い、合併症を防ぐことが重要です。

